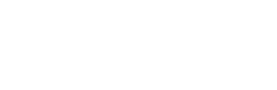教員紹介
一人ひとりの個性と多様な意欲を伸ばす実践型の指導で、
現代に求められる教育者・保育者を育成します。
保育学部長からのメッセージ

豊かな知識や技能を最大限
活かすことができる教師・保育士へ
教育・保育現場で、皆さんが直面する課題の多くは答えが一つとは限らないものばかりです。この時、非常に重要なのは知識や技能の獲得とともに、これらをどのように活用できるかということです。ここに、教師・保育士としての真の力が表れると思います。これから始まる4年間の学生生活において、この基盤をしっかりと育ててください。さまざまなことに興味をもって新たなことに挑戦したり、失敗してもくじけずに継続し続けたりすることで、学びの芽は育っていきます。子ども一人ひとりの健やかな育ちを支えるためには指導者自らも成長し、探求的な心を育てることが重要です。
保育学部長
淺野 卓司 教授
保育学科
-

教授辻岡 和代
ゼミナールテーマ:子どもの食と栄養
食の可能性は無限大、
子どもの興味を広げる教育者・保育者へ。担当科目/子どもの食と栄養Ⅰ・Ⅱ、家庭
食育、好き嫌いや食物アレルギーをはじめ、ゼミでは子どもの食と栄養に関して幅広く探究しています。各自が興味あるテーマに取り組み、みんなでアイデアや意見を出し合って学ぶため、ゼミ生全員分の食のテーマや知識を修得できるのが特色です。またゼミで開催する小学生、乳幼児の親子を対象としたクッキング講座に参加し、子どもたちが食に感じる驚きや不思議を目の当たりにします。子どもの興味をさらに広げることができるよう、教育者や保育者は専門知識とともに食への好奇心や探究心を持つことを忘れないでほしいと思います。ゼミで「食の可能性は無限大」と感じる経験をいっぱいして、将来に役立ててください。 -

教授太田 早津美
ゼミナールテーマ:保育実践力を高めるための学び
(手作りおもちゃ、絵本ワークショップ)遊びを考え、創作するなかで、
保育者に必要な実践力を鍛える。担当科目/乳児保育Ⅰ・Ⅱ、家庭支援論、保育実習指導
身近な材料を利用した手づくりおもちゃや手づくり絵本の制作など、発想やアイデアをこらした創作活動をしています。また、絵本ワークショップや小麦粉粘土遊びでは、地域の親子が遊びやものづくりを楽しめるワークショップを企画・開催します。こうした学びを通じて、身につけてほしいのは、創造力や企画力、そしてチームワークによる協調性。どれも、将来保育者として働くうえで役立つ実践力になります。
-

学科長 教授
寺田 泰人担当科目/
保育内容指導法(健康)、
幼児体育ゼミテーマ/子どもとスポーツ
私はスポーツ科学を専門としています。みなさんは「スポーツ」の語源が"気晴らし"や"遊び"であることを知っていますか?また「子どもは遊びの天才」と言われますね。ゼミナールでは、子どものスポーツや運動遊びを通して、子ども理解を深めていきます。 -

教授
伊藤 茂美担当科目/
保育内容総論、教育実習Ⅰゼミテーマ/保育・幼児教育における実践研究
言葉にできない思い、表情や行動の内にある思いなど、子どもの様々な思いを捉えることから保育は始まります。 一人一人を理解し、子どもの興味や関心、発達に応じた関わりができる保育者をめざし一緒に学びましょう。 -

教授
上村 晶担当科目/
保育者論、
保育カリキュラム論ゼミテーマ/子ども理解・保育方法の研究
社会の変化に応じて求められる保育者のあり方について、みなさんと一緒に考えていきます。小さな気づきを共有しながら、理想を描いてほしいと願っています。 -

教授
小原 倫子担当科目/
子ども家庭支援の心理学、
教育相談 A・Bゼミテーマ/乳幼児の情動、子育て支援
子どもを取り巻く周りの人たちが、子どもを理解し、子どもを育てる養育者を支援することは、子どもと養育者が生きていくことは楽しいんだと感じる力になります。子どもと養育者が自らを肯定し、社会に適応していく過程をどのように支えるかを一緒に考えていきましょう。 -

教授
柏倉 秀克担当科目/
障害児保育、
特別支援教育論ゼミテーマ/特別な教育的ニーズがある子どもの理解と支援
子どもたちのすこやかな成長を支援するため、子どもたちが内面に抱える問題と子どもたちを取り巻く環境の両面から学びましょう。 -

教授
金子 晃之担当科目/
教育原理、教育制度ゼミテーマ/教育・保育の問題全般
人間の原点は、乳幼児期にあります。その時期に、どのように愛され、どのように人や物と関わったかの質が大切。その質保証が「保育」です。桜花保育はそのスペシャリストを丁寧に養成します。学生同士、学生と教職員との関わりの良さは他校に見られないレベルです。 -

教授
嶋守 さやか担当科目/
現代社会と女性、地域社会ゼミテーマ/子どもたちの幸せな社会づくり
子どもたちと子どもたちをとり囲む環境づくりをより良くするために「私たちは何ができるのか」を考えています。障がい児とともに育ち合うこと、またスウェーデンの幼児教育プログラムについても学びます。 -

教授
古畑 淳担当科目/
社会福祉、
子ども家庭福祉Ⅰ・Ⅱゼミテーマ/子ども家庭福祉の制度についての研究
子どもの生活と成長発達の権利を保障するための制度・法システムについて学んでいきます。4年間の学びの中で、「子どもの最善の利益」とは何かについて考えていきましょう。 -

准教授
小柳津 和博担当科目/
障害児保育、
肢体不自由教育論Ⅰ、
病弱教育論ゼミテーマ/障がいや病気のある子どもの保育・教育
障がいのある子どもへの支援のあり方について考えることは、すべての子ども達にとって理解しやすい支援方法を工夫することにつながります。すべての子ども達の成長を支える教育者・保育者をめざし、特別支援教育についてともに学びましょう。 -

准教授
勝浦 眞仁担当科目/
障害児保育、
発達障害の理解ゼミテーマ/障がいや病気のある子どもの保育と教育
障がいや病気のある子どもたちは教育・保育の場で楽しく生き生きと活動したいという思いを持っています。その思いに応えられる保育者をめざして、ともに学んでいきましょう。 -

准教授
基村 昌代担当科目/
幼児音楽、芸術の世界ゼミテーマ/子どもの音楽劇制作
音楽の楽しさを味わい、その魅力や奥深さを感じる感性を磨くことを目標としています。ゼミではオペレッタなどの舞台制作も行っています。学生時代の経験を力に変えて、教育・保育の現場で発揮できる力を磨きましょう。 -

准教授
堀 由里担当科目/
教育心理学、発達心理学ゼミテーマ/子どもの心理発達、対人関係の心理学
「かくれんぼ」をして遊んでいても隠れきれていない子どももいます。子どもも大人も一つひとつの行動の裏にはさまざまな心理があります。モノの見方や思考、感情など私たちの心を丁寧に理解して、保育実践につなげられるよう、一緒に学びましょう。 -

准教授
松永 康史担当科目/
道徳教育の指導法、社会科教育ゼミテーマ/授業づくり、実践検討
子どもたちの「なんで?どうして?」というはてなを、一緒に考えていけるような授業や学校、先生の在り方を考えていきましょう。みなさんが抱いている社会や教育の疑問も一緒に考えていきましょう。 -

准教授
森川 拓也担当科目/
幼児と言葉、国語科教育法ゼミテーマ/「言葉」と教育・保育
私たちは、言葉の意味と使い方を知らないまま生活しています。だから教育・保育の場で、言葉の意味を使って「読む・書く・伝える・考える」ことを教える必要があるのです。そのための「国語」です。「言葉」をしっかりと学び、優れた教育者・保育者をめざしてください。 -

助教
五十嵐 睦美担当科目/
幼児音楽、幼児と表現ゼミテーマ/子どもの音楽表現と指導法
子どもたちは先生の歌声や動きなどの表現を感じ取って育ちます。そこでゼミでは、さまざまな音楽体験を通して表現力を磨き、音や音楽で子どもたちとかかわる方法について考えていきます。教育・保育の場で音楽表現の楽しさを伝えられる先生を目指して、ともに学んでいきましょう。 -

助教
内田 将平担当科目/
教育の方法、教育課程論ゼミテーマ/海外の教育方法・カリキュラムの研究
人間形成を支える〈仕掛け〉の方途はどうあるべきなのか。私の専門であるドイツをはじめとする諸外国の教育も参照しながら、教育の方法・内容のあり方についてともに学びましょう! -
- 客員教授
- 柴田 竹代
- 谷田沢 典子
- 樋口 桂子
- 石月 静恵
国際教養こども学科
-

教授石山 英明
ゼミナールテーマ:子どもと楽しむ音楽活動
音に対する心の動きが、
子どもたちへの気づきにつながる。担当科目/幼児音楽、芸術の世界、基礎演習Ⅰ
私の専門は、保育・幼児教育における音楽活動です。将来子どもに音楽を指導するうえで、まずは音に触れる楽しさや喜びを、子どもの視点で気づくことが大切です。そこで、ゼミでは自然の音を探しに出かけたり、あるいはさまざまな楽器に触れたりします。日常の美しいものに触れることを通じて、自分自身の心が動く体験をしてほしいからです。また、こうした体験が、子どもたちへの気づきにもつながると考えています。何かを発信したり、表現したりしているのは、決して自然や楽器だけではありません。子どもたちも常に何らかのメッセージを発信しているものです。音を通じて豊かな感受性を磨き、さまざまなことへの気づきにつなげて、人としても成長してほしいと思います。 -

准教授田端 智美
ゼミナールテーマ:子どもの造形
国を問わず、世界の子どもが楽しめる
造形について学ぶ。担当科目/幼児造形、幼児と表現、保育内容指導法(表現)、教育実習
手づくりのおもちゃに子どもたちは大喜びします。また、絵を描いたり、創作したりすることが、子どもたちは大好きです。こうした造形活動は、言葉を必要としないことから、国を超えて日本はもちろん、世界共通で誰もが楽しさを実感できる遊びです。子どもの造形活動について理解を深めながら、国を問わず、世界の子どもたちが楽しめるスキルを身につけてほしいと思います。また、1年次の海外研修で行ったニュージーランドの保育施設では、自国のマオリ文化に誇りを持っていました。子どもたちも遊びにも文化を取り入れている点が印象的でした。こうした海外の保育を通じて視野を広げ、一方では日本文化も理解し、自国の文化や遊びを世界に発信できる保育者になってほしいと思います。
-

学科長 教授
木村 達志担当科目/
保育内容指導法(健康)
幼児体育ゼミテーマ/子どもの健康、子どもの運動遊び
子どもの健康の3本柱は、「遊ぶ、食べる、寝る」で構成されます。保育者をめざす皆さんと、よりよい「遊ぶ、食べる、寝る」を考えていきたいと思います。また、自分自身の健康もしっかりと管理ができるように学びます。 -

教授
佐久間 潔担当科目/
コンピュータⅠ・Ⅱゼミテーマ/こどもとICTにふれる
現代社会は、ICTが当たり前に切っても切れない存在となっています。保育者を目指す皆さんには、新しいICTを使った子ども教育を考えるため多くの経験をして欲しいと思います。3次元プリンタによる子ども玩具を考えたり、ドローンを使って子どもたちを観察したり。たくさんの新しい経験を積んで楽しい保育を考えてみましょう! -

教授
髙橋 一郎担当科目/
多文化共生研究、
国際関係論、地域研究Ⅰゼミテーマ/伝統文化と保育現場
長期留学先であるオーストラリアは、多文化主義という文化の多様性を受容する国です。しかし、歴史的に見た場合、白豪主義をはじめ、明暗入り混じった多くの事実に行き当たります。留学前に、学際的なアプローチのもとオーストラリアについて一緒に学びましょう。 -

教授
ダーリンプル 規子担当科目/
乳児保育Ⅰ、
子ども理解の理論と方法ゼミテーマ/関係性の中で育つ子どもと保育
赤ちゃんは、人を求め、響き合う関係性の中で育っていきます。子どもたちの行為・あそびはすべて大切な意味を持っています。保育者として、自分を見つめ、保護者を支えながら、子どもたちが豊かに育つことにかかわる-そんな奥深く素敵なこと、いっぱい探究してみましょう。 -

教授
寺田 恭子担当科目/
チームビルディング実践・
スポーツ健康論、幼児と健康ゼミテーマ/障がいのある子どもの身体活動
私は"車いすダンス"を軸として、障がいのある人たちの身体とスポーツに関する研究をしています。障がいのある子どもたちの命がより輝くような活動や研究を一緒にやりましょう。情熱をもって学び続けて! あなたの可能性は無限大だから。 -

准教授
内田 政一担当科目/
総合英語、
ことばのメカニズム、
Study Abroad Preparationゼミテーマ/子どもの言語獲得
英語を学ぶということは、文法のルールを丸暗記することではなく、ネイティブの感覚を身につける手段を学ぶことです。言語そのもののメカニズムから子どもが言語を獲得していく過程まで、英語を中心とする言語に関するあらゆることについて一緒 に学んでいきましょう。 -

准教授
小野 克志担当科目/
海外保育フィールド・スタディ、
海外の保育
Study Abroad Preparationゼミテーマ/保育の英語
海外の保育・幼児教育の実際を学び、専門的視野を広め、異なるものの見方や考え方に気づくことによって自らの思考を深めることを目指します。海外保育ライセンスプログラムで得る経験や人脈は何にも代えがたい将来の財産になるはずです。 -

准教授
加藤 あや美担当科目/
異文化理解、総合英語、
Teaching English for Childrenゼミテーマ/異文化コミュニケーション、早期英語教育
言語や文化について学ぶことは、自分と異なる他者を理解する最初の一歩です。子どもに焦点を当てながら、効果的な言語の指導法について理論と実践の両側面から学んでいきます。異文化コミュニケーションの楽しさを伝えられる保育者を目指しましょう。 -

准教授
森山 雅子担当科目/
発達心理学、教育心理学、
教育相談ゼミテーマ/子どもの心理的発達、保護者の心理的発達
「子どもっておもしろい!すごい!」と素直に感じることは、保育者においてとても大切な心の動きです。子どもの面白さをより深く理解するために、子どもの心理や発達、それに伴う保護者の心の動きについての理論や方法論を一緒に学びましょう!